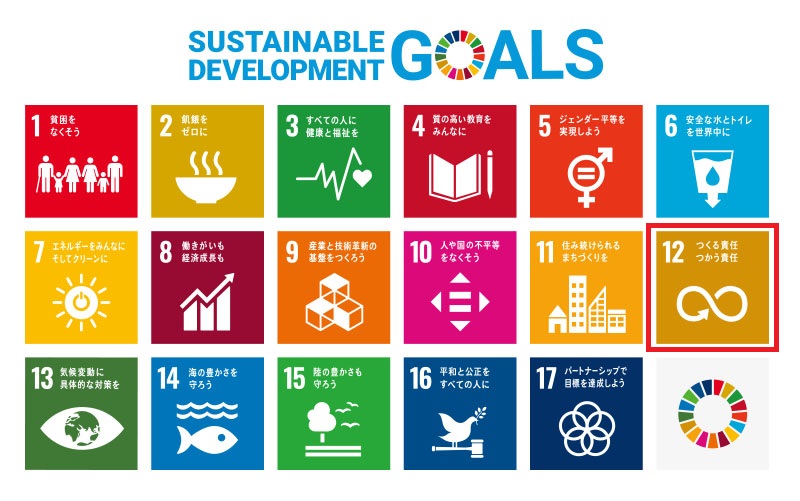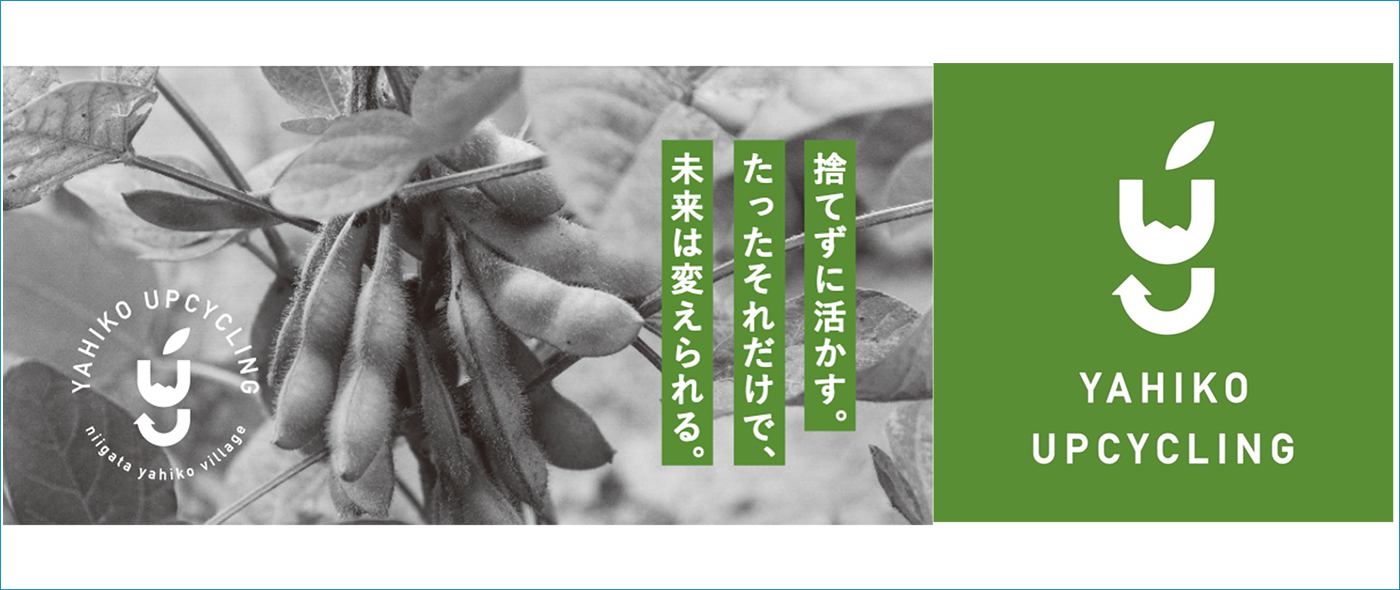
新潟県弥彦村発 規格外茶豆を活用したアップサイクル事業「YAHIKO UPCYCLING」8月23日(土)より開始
YAHIKO Avenir合同会社とヤヒコロジー株式会社は、弥彦村産の規格外茶豆を有効活用し新たな価値を生み出すアップサイクル事業「YAHIKO UPCYCLING」を開始します。
YAHIKO Avenir合同会社(新潟県弥彦村、代表:藁科克彦)とヤヒコロジー株式会社(新潟県弥彦村、代表取締役:佐藤行成)は、弥彦村産の規格外茶豆を有効活用し新たな価値を生み出すアップサイクル事業「YAHIKO UPCYCLING」を2025年8月23日より開始します。本事業の第一弾として、茶豆の魅力を活かした「YAHIKO CHAMAME POTAGE」「YAHIKO CHAMAME SALT」「YAHIKO CHAMAME ICECREAM」の3商品の販売を開始します。
両社は本取り組みを通じ、新潟県弥彦村の地方創生構想に基づいた「弥彦村モデル」としてゼロエミッション農業 × 地域資源循環 × エシカル消費のモデルケースとなることを目指します。
事業URL: https://yahikoavenir.jp/yahikoupcycling/
豊かな自然環境に恵まれた新潟県弥彦村では、多種多様な農産物が古くから生産されてきました。しかし、その中でどうしても避けられないのが「規格外品」の存在です。例えば枝豆の場合、出荷時の選別で約40%以上が規格外としてはじかれ、その多くが畑に戻されるか、廃棄されています。味や品質に問題はないにもかかわらず、“見た目”の基準だけで市場に出せないのが現状です。
この“もったいない”をなくし、地域資源を生まれ変わらせるために立ち上げたのが「YAHIKO UPCYCLING」です。規格外品を粉末化し、保存性や活用の幅を広げることで、廃棄削減と新たな産業価値の創出を両立します。今回の枝豆での挑戦は、今後、他の農産物にも広げていく予定です。
※:捨てられてしまうはずだった素材に新しい価値を与えて、より良いものとして生まれ変わらせること。リサイクルが「元に戻す」のに対し、アップサイクルは「より価値の高いものに変える」ことを目指します。
「YAHIKO CHAMAME POWDER」は、枝豆選果場から出る規格外の茶豆を有効活用し、実はもちろん莢(さや)までまるごと粉末化した茶豆パウダーです。独自の高速乾燥技術によって、弥彦ブランド茶豆ならではの豊かな香りと甘み、そして栄養をそのまま閉じ込めました。無添加・無着色の安心設計で、他社では再現が難しい高レベルの“香りと風味”を実現しました。お菓子やスープ、パン、プロテイン、ペットフードなど、幅広い用途でご利用いただけます。
美味しくて、エコな逸品「YAHIKO CHAMAME POWDER」を、ご家庭でも気軽に楽しんでいただけるよう商品化しました。どの商品も、生産者の想いとこだわりが詰まった一品です。
2. YAHIKO CHAMAME SALT
弥彦の茶豆ソルト 〜寺泊釜焼き塩使用〜
弥彦村は、天照大神の曾孫である天香山命が越後に農耕や漁業・製塩技術などを伝えたとされる越後文化発祥の地です。越後一宮である弥彦神社のお膝元として古来より語り継がれてきたこの地で持続可能な暮らしへの願いを込めて作られたのが「弥彦の茶豆ソルト」です。寺泊伝統の釜焼き塩と、弥彦村産の香り高い茶豆を合わせた無添加・無着色の調味料で天ぷらや焼き物など、様々な料理の素材の味を引き立てます。弥彦産の旨みたっぷりな茶豆と、寺泊産の釜焼き塩を組み合わせた無添加・無着色の香り豊かな調味料。天ぷらや肉・魚の焼き物など、様々な料理の味を引き立てます。
■「YAHIKO UPCYCLING」プロデューサー
藁科 克彦(わらしな かつひこ)画像:右
YAHIKO Avenir合同会社 代表
地域商社機能で農業と産業をつなぐ地方創生の旗振り役。全国で新事業創出や地域資源活用を推進し、2024年弥彦村で起業。規格外枝豆のアップサイクルや特産品開発に取り組み、「弥彦モデル」を全国へ発信。
佐藤 行成(さとう ゆきなり)画像:左
ヤヒコロジー株式会社 代表取締役
全国規模のプロモーション経験と地元愛を併せ持つPRスペシャリスト。大手化粧品メーカーや、大手食品メーカー、渋谷再開発などのPRを手掛け、2024年に起業。観光・ブランド戦略で弥彦の魅力を全国へ届ける。
YAHIKO Avenir合同会社
所在地:新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦2487-1
代表者:代表 藁科 克彦
事業内容:地域活性化事業、農産物の高付加価値化・特産品開発、地域商社機能
ヤヒコロジー株式会社
所在地:新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦1143-16
代表者:代表取締役 佐藤行成
設立:2024年6月
事業内容:地域資源活用・ブランディング、PRコンサルティング
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する
4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。